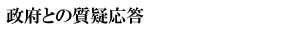 |
|
| −「積極財政が財政を健全化する」ことを安倍首相は「誤差」に言及しつつも認める− |
|
|
 |
| 滝実衆議院議員により、第四回の質問主意書を出したところまで、『質問主意書を利用した内閣との質疑応答』で説明したが、ここでその続きを書く。 |
|
|
|
| 10.答弁書 【第五回答弁】 平成19年5月15日 |
|
 |
|
| 政府は平成18年度内にデフレから脱却すると公約しながら、それは守れなかった。そこで質問をした。 |
|
| 【第四回質問】政府はデフレ脱却に向けてどのような政策を行っているのか。デフレ脱却に失敗し、経済を低迷させたために、かつて日本の国民一人当たりの名目GDPは世界一だったのに、平成十七年度には十一位まで落ちたし、世界のGDPに占める日本の比率が平成十年の17%から平成十七年の10.3%まで落ちたではないか。 |
|
| 【第四回答弁】「平成十九年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」に書いてあるから参照せよ。世界のGDPに占める日本の比率が下がったのは、世界経済が順調に成長する中で、日本経済がデフレ状況にあったことが主な原因だ。政府は適切な経済運営に努めてきた。 |
|
| 【第五回質問】「平成十九年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」にはデフレ脱却に有効な政策は何一つ書いてない。どの政策がどれだけデフレ脱却に役立つかと言うのか。世界のGDPに占める日本の比率が平成十年の17%から平成十七年の10.3%まで落とした政策が「適切」と言えるのか。 |
|
| 【第五回答弁】この質問に対しては、第四回答弁を繰り返したのみ。デフレ脱却に対しては何もやっていないことを事実上認めた。この政策が「適切」であるという暴言を問いただしたことに対してはノーコメントだった!コメントできるわけがない。 |
|
| 【解説】日本経済が没落した理由は、デフレであると政府が認めたということは、大きな一歩である。自分たちのお陰で日本経済が立ち直ったなどとは言わせない。 |
|
 |
|
| 【第四回質問】政府・日銀が歳出を抑制し、短期金利を引き上げていく政策は、デフレ脱却を妨げる政策ではないか。 |
|
| 【第四回答弁】政府としては、極めて厳しい財政状況等を踏まえれば、経済成長と財政再建の両立に努め、安易な財政出動に頼らない安定的な経済財政運営を行うことが必要であると考えており、また、本年二月二十一日の日本銀行による政策金利の引上げは、中長期的に、物価安定を確保し、持続的な成長を実現していくことに貢献するとの考え方に基づいて行われていると承知している。 |
|
| 【解説】これはもちろん質問に対する答えになっていない。デフレ脱却を実際妨げているのだから、このように答えるしかない。 |
|
 |
|
| 【第四回質問】経済生活問題が原因の平成十七年の自殺者数は、平成二年の六倍程度にまで増加している。平成七年には六〇万世帯であった生活保護世帯が今や一〇〇万世帯を超えている。 |
|
| 【第四回答弁】五についてで述べた経済財政運営の考え方に基づき、安定した経済成長を続け、経済社会の各層に雇用拡大や所得の増加という形で成長の成果を広く及ぼすことにより、国民が未来に夢や希望を持ち、より安心して生活できるような社会の実現を目指す必要があると考えている。 |
|
| 【解説】世界経済は過去30年間で最良の状態にあるという中で、日本では経済政策の失敗で、これだけ多くの国民が苦しんでいることを、政府に知らせることは重要である。政府はそれを認めるわけにいかないから、苦し紛れにこのような見当はずれの答弁しかできない。 |
|
 |
| 現在の厳しい財政事情を克服するため、経済財政モデルによる分析の結果を役立てたらどうか |
|
| 【第四回質問】厳しい財政状況を踏まえれば経済成長と財政再建の両立に努めるべきであることは明らかである。それを実現するためには、政府の経済財政モデルによる試算にしたがって財政出動をして債務のGDP比を減らすべきではないのか。 |
|
| 【第四回答弁】内閣府の経済モデルは、誤差を伴うため、相当の幅をもって解釈すべきだ。その計算結果を参考にしつつも、その時々の経済状態を十分に踏まえて総合的に判断すべきだ。 |
|
| 【解説】自分の都合のよいときには、経済モデルを使い、都合の悪いときには使わないでよいような文章を作文している。根底に流れる考え方は、経済モデルは自分の都合のよいように作らせて、都合のよいように使う。経済の発展、国民の幸福のための経済モデルではなく、財務省の、財務省による、財務省のための経済モデルである。 |
|
 |
|
| 【第五回質問】政府は過去十数年間、デフレ脱却のための様々な政策を行ってきており、そのことごとくが失敗に終わり、その結果デフレはまだ続いている。それが原因で、世界のGDPに占める日本の割合が激減しつつあるのが現状であることは、答弁書でお認めになった通りである。過去の政府の政策でデフレ脱却に失敗した理由は何か。 |
|
| 【第五回答弁】日本経済は、物価が持続的に下落するという意味でのデフレ状況にはない。政府として、海外経済の動向などにみられるリスク要因を考慮しつつ、このデフレ状況に戻る可能性がないかどうか、注視していく必要があると認識している。 |
|
| 【解説】これはまあ、なんという答弁だろう。物価が持続的に下落するという意味でのデフレ状況にはない??デフレーターが、ずっとマイナスであるということは、GDPに関連する物価が持続的に下落するという意味でのデフレ状態だろう。そのデフレが日本経済を没落させていると認めておいて、何を言い出すのか。政府の対応としては「注視」していくだけで十分なのだろうか。 |
|
 |
| 日本はアメリカの3.7分の1しか名目GDPを伸ばすことができないのか。 |
|
| 【第五回質問】アメリカの成長率は、日本の3.7倍である。日本はこれだけしか成長できないのか。 |
|
| |
2005年度 |
2006年度 |
2007年度 |
| 日本 |
1.0% |
1.5% |
2.2% |
| アメリカ |
6.3% |
6.3% |
5.0% |
|
| 【第五回答弁】米国に比べて日本の名目成長率が低かったことの主な要因としては、世界経済が順調に成長する中で、日本経済がデフレ状態にあったことなどが挙げられると考えている。 |
|
| 【解説】日本はデフレ経済だから、アメリカの3.7分の1しか成長できないのだという。だったら、デフレ脱却を最重要課題にすればよいだろう。国の借金の名目GDP比を、あれだけ問題にしているのだから、名目GDPの拡大は、あまりにも重要だ。名目成長率が高まれば、賃金も上がるし、国民も豊かになるし、消費も増えるし、地方自治体の財政も改善するし、国の借金のGDP比も減ってくるし、やっと日本経済にも春がくる。 |
|
 |