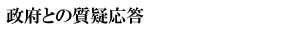 |
| 2006年3月8日の予算委員会での秋元司議員の質疑に関するコメント |
|
 |
| 秋元氏の質問時間は13分に限られていて、一方質問に答える側は、いくらでも長く時間を使ってよいのだそうだ。こういう条件で、論戦をやれば答える側が圧倒的に有利になる。こういう慣例が参議院にあるわけで、悪習と言えるのではないだろうか。当然質問者と答弁を行う人とは、平等に時間を持つべきだろう。 |
|
 |
|
| |
定率減税は、もうご承知のように、平成11年、小渕内閣のときに当時大変危機的な経済情勢でございましたから、その底割れを何とか税制でもって支援できないかということで導入された、危機対応というものであったと私は思っておりますが、厳しい財政事情のもとでございますから、見合いの財源なしに将来世代の税負担によって賄われている・・・ |
|
| と述べた。しかし、内閣府の試算では、減税により債務のGDP比が下がることが分かっている。そうであれば、減税により将来世代の税負担を軽減することになるから、谷垣大臣の発言は正しくない。今でも異常な低成長であることと、まだデフレが続いていることを考えれば、危機が去ったと考えるべきではない。 |
|
 |
| ● |
財政難とは債務の額そのものが問題か、債務のGDP比が問題なのかという質問に対する谷垣大臣の答弁 |
|
| |
プライマリーバランスを回復した後の財政再建の目標は何なのかということに関連してまいりますので、今結論を持っているわけではございませんけれども、なかなかその、残高そのものを抑えていくという目標を立てるのはそう簡単ではございませんで、GDP比で圧縮をしていくということが目標なのかなと自分の頭の中では思っております。 |
|
| この発言は極めて重要で、これまで財務省は債務のGDP比でなく債務の額そのものが重要なのだと主張する傾向があった。財務大臣自らこのように発言したことは、今後財務省に対して、反論の材料として極めて重要になる。つまり、「債務はいくら増えてもいい、GDPがそれ以上に増えればよいだけだ」ということを財務大臣が確認して下さった。 |
|
 |
| ● |
斉藤計量分析室長の発言により、内閣府は今年の「改革と展望」では、昨年のものに変更を加えていることが明らかになった。5兆円所得税増税すると1年目で7.1兆円もGDPが減るという昨年のモデルでは、今回の増税を国民に納得させることができないと判断したのだろう。内閣府に直接質問したら、今年のモデルでは5兆円の所得税増税で3.9兆円しかGDPが減らないように、消費関数を変えたとのこと。ただし、2年目には6.5兆円の減少となり大差は無くなる。具体的には増税して可処分所得が減っても、国民は消費を余り減らさないと仮定したとのこと。なぜそのような仮定をしたのか。ラチェット効果を入れたとのこと。ラチェット効果とはいったん手に入れたゴージャスな生活に慣れてしまうと、そこの地位に慣れてしまい(歯止めがかかり)、元のゴージャスでない生活には戻れない、という人間の心理が反映された経済現象のことをいう。 |
|
| ということは、2005年度までは日本国民はゴージャスな生活を手に入れていた。しかし今回の増税によって2006年度には、収入が減ったのに、このゴージャスな生活が手放せなくなっているだろうから、消費はそれほど減らない。つまりGDPの減少は少ないと内閣府は判断したということだ。しかし、実際は下図で分かるように雇用者報酬は長期低落傾向にあり、2005年度が収入の頂点であったわけではない。ここまで収入を減らしておいて、更に減らそうという過酷な話だ。ラチェット効果でGDPの落ち込みを防ごうというのは無理があるのではないか。それに、収入が減っても国民は多く消費するだろうと期待して、GDPの落ち込みは少ないだろうという政府の考えは、甘えともいえる。消費が落ち込んでいるとき、消費を伸ばしたいのであれば、可処分所得を増やすのが正しい政策だろう。 |
|
|
 |
| ● |
増税、国民負担率を上げなかった場合のシミュレーションについて聞かれて斉藤計量分析室長は、そういうものはやっておりませんと答えた。基準解を求めずしてどうして差分が計算できるのか。彼らは増税後の結果を発表し、乗数も発表しているのだから、増税後の結果から差分を引けば基準解が出る。これは小学生もできる簡単な計算だ。やっていなかったとしても、1分もあればやれる結果だ。いずれにせよ、増税によりGDPも可処分所得も下がり、失業率は上がり、デフレは悪化し、債務のGDP比も上昇して財政は悪化するという結論は、今年のモデルでも昨年のもでも変わりはないということは内閣府は認めている。そうならば、何のための増税なのだろうか。今回の家計負担の増加分は2兆円程度で、大部分が所得税定率減税の半減である。仮に、2兆円の全部が所得税関連であったと仮定し、2兆円は、GDPの0.4%だと近似して内閣府の試算を使ってみよう。 |
|
|
| |
[2005年発表] |
[2006年発表] |
| 1年目 |
2年目 |
1年目 |
2年目 |
| 名目GDP |
2.84兆円減少 |
3.08兆円減少 |
1.56兆円減少 |
2.52兆円減少 |
| 実質GDP |
0.42%下落 |
0.28%下落 |
0.26%下落 |
0.35%下落 |
| 物価 |
0.18%下落 |
0.36%下落 |
0.06%下落 |
0.19%下落 |
| 国・地方の債務のGDP比 |
0.48%上昇 |
0.22%上昇 |
0.12%上昇 |
0.07%上昇 |
| 可処分所得 |
0.98%下落 |
1.10%下落 |
0.91%下落 |
1.07%下落 |
| 失業率 |
0.06%上昇 |
0.06%上昇 |
0.04%上昇 |
0.07%上昇 |
|
|
| 2005年発表のモデルと2006年発表のモデルで若干異なる。しかし、その差は重要ではなく、両モデルともすべての経済データは悪化の方向を示している。つまり、増税は景気を悪化させ、デフレも悪化させるだけでなく、債務のGDP比も悪化させている。財務省は、債務そのものを減らそうというのでなく、債務のGDP比を減らそうというのだから、所得税増税は害あって益なしであることがはっきりした。 |
|
 |
| ● |
日本の名目成長率は低すぎることが指摘され、それに対する与謝野大臣の答えは、名目GDPはいくら低くても、実質GDPが高ければ実質的に豊かになっているのだと言いたいようだ。名目GDPは物価変動が除かれてないから意味がない数字だと言いたいのだろうか。そうだとすれば、これは与謝野大臣が経済をまるで理解していないことを証明するような発言だ。ではGDPの国際比較をしようとしたとき、実質で比較しようというのか!?実質GDPは、国内で自国通貨でGDPを評価したときに、その国の過去のGDPと比較する場合でしか意味がない。ドル表示でGDPを表して長期間のGDPの推移を国際比較するときは、「名目」とは言っても実質的な経済規模を比較していることになる。 |
|
 |
| ● |
財務省の試算について与謝野大臣が説明をしている。3%成長と4%成長を比較したときの財政収支がどうなるかということだ。大臣の議論は国債の利払いのことだけを取り上げて、国の利子収入を無視している。更に重要なのは、4%成長のほうが、3%成長より1%だけGDPが大きくなり、それが債務のGDPを1%だけ減らすということだ。債務を1%減らそうと思えば財政収支を8兆円程度改善しなければならない。つまりGDPを1%増やせば、財政収支を8兆円改善したことに相当する。このことに注意すれば、『ただ成長率を上げていけば、財政が余裕が出てくるという単純な話ではない』という与謝野大臣の発言が正しくないことが分かる。実際『成長率を上げていけば、財政に余裕が出てくる』ことは疑う余地もない。 |
|
 |
| ● |
与謝野大臣の発言は、質問の意味を誤解していることがわかる。質問の意図は長期金利が上がっても、日銀が多く国債を保有していれば、利払いは日銀を経由して国庫に戻るではないかというもの。与謝野大臣は、国債の買い入れを長期金利上昇を抑えるためと誤解して答弁をしている。その次の質問で「デフレ克服には日銀と政府が一体となるべきだ」という意味を与謝野大臣は、また誤解したようだ。デフレ克服のための日銀と政府の協力とは、日銀が買いオペをして資金を提供し、政府がそれを財政に使ってデフレを克服するという意味だ。与謝野大臣は日銀の政策決定会合での決定に従うことが、日銀と政府の「協力」だと思っているようだ。余程、平易な言葉で説明してやらねば、与謝野大臣は理解できないようだ。金融担当大臣としての資質が疑われる。 |
|
 |